みなさんこんにちは!
これまで、家づくりの流れの一部をご紹介していきました。
下調べ編と、折衝編に分けてご紹介していますので、
そちらもぜひご覧ください。
今回は、契約後の詳細打合せから実際に工事が始まり、
家が建つまでの流れをご紹介させていただきます!
家の詳細打合せは結構疲れる

契約までに、間取りの打ち合わせはしていますが、
契約後はさらに詳細な打ち合わせが始まります。
土地に対して、どのように建物を配置するか。
間取りを確定させて、どんな窓にして、どんな建材を使い、
どんな設備を入れるかなど、細かい打ち合わせをすることになります。
まず、この詳細打合せが始まるまでに、やっておくことがいくつかあります。
- 新しい家に持っていく家具、家電をリストアップし、採寸する
- ある程度設備や建材の下調べをしておくこと
- 不要なものは捨て始めること
新しい家で使いたいものをリストアップして採寸するのは非常に重要なことです。
というのも何をどこに置くか、どう置くかが決まらなければ
建具のサイズやコンセント位置が決められず、
打合せが進まないからです。
また、打ち合わせではショールームに行く可能性があります。
ショールームはたくさんの設備や建材を見ることができ、非常に楽しいのですが、
反面、悩み始めると大変なことになります。
そうならないために、ある程度下調べをして目途をつけてから
ショールームに行くようにしましょう。
最後は不用品の処分ですが、打ち合わせが終了したらすぐ
建物の解体が始まります。それまでに引っ越しをしなければならないので、
意外と時間がないんです。そうなってから焦らないために、
早めに準備しましょう。
実際に打ち合わせが始まると、下記のような内容を決めていきます。
- 建物の配置、高低差
- 間取り
- 窓配置、窓サイズ
- 内装建材
- 設備
- 電気関係
- 外構
「え!そんなことまで決めるの?」というものも、打ち合わせの内容に入っています。
選択肢が少ないような住宅会社でも、なかなか上記のすべてを一日で決めていくのは
難しいと思います。
自分たちのこだわりばかりを主要するのではなく、しっかりとプロの意見を
聞くようにしましょう。良いと思ったことでも、プロから見たら
使いづらそうだなーと思うことがあります。
もちろんプロは助言をしてくれるはずなので、
頑固にならずそういった助言に耳を傾けることが大切です。
失敗しても、すぐ建て直したりできませんからね。
詳細打合せは決めることだらけ。一日では終わらないので、
しっかり事前準備して挑みましょう。頭は柔らかく、
色々な意見に耳を傾けましょう。
確認申請提出 もう変更はできません
建物の基本構造や配置、窓サイズなどが決まると、
確認申請を提出することになります。
確認申請機関というものがあり、そこに
「こんな家を建てるけど問題ありませんか?」と確認するための工程です。
逆に言うと、確認申請が受理されてしまうと
建物の構造部分や配置、窓の変更はできないと考えた方がよいです。
もしどうしても変更したいという場合は、担当設計に相談する
必要がありますが、少なくとも再度確認申請を提出(変更)する必要があるので、
数万円~数十万円単位で費用がかかってしまいます。
ですので、確認申請を提出する前に、しっかりと健闘しておく必要があります。
確認申請提出後の変更は基本NG。
だからこそしっかり検討して決めましょう。
いよいよ仮住まいへ引っ越し

確認申請が無事受理され、詳細打合せが終了すると
いよいよ家の解体作業が始まります。
その前に、仮住まいに引っ越さなければなりません。
そもそも、仮住まいはどこで探すのでしょうか。
基本的には、建設会社とつながりのある仮住まい業者がいますので、
営業マンに確認してみましょう。
一般的な街の不動産屋さんに行っても、なかなか仮住まいを見つけることができません。
というのも、街の不動産屋さんで扱う物件のほとんどが「普通賃貸借」の物件だからです。
普通賃貸借の多くは2年間の契約で、2年たつと自動更新されていくような物件です。
一般的な賃貸を探すのであればこれでいいのですが、
こういった物件は長く住んでもらうことを前提としているため、
家の建て替え期間のみの期間限定で借りることを嫌がられます。
だからこそ、仮住まい用の物件というものがあり、
それを専用で扱う業者がいるのです。
仮住まい用の物件とはどんなものかというと、
転勤で一時的に家を空けるから、その間期間限定で賃貸に出しているものなどです。
仮住まいを決めるタイミングをご紹介します。
- 住宅の契約をしたら、仮住まい業者とコンタクトをとります。
- 希望条件などを伝えて、詳細打合せ期間中に何件か内見します。
- 詳細打合せが終了するまでに、物件を決めて契約します。
- 詳細打合せが終わったら、引っ越しをして解体が始まります。
上記の流れとなります。
仮住まいは仮住まい専門業者に依頼しましょう。
詳細打合せ終了までに、物件を決めること!
いよいよ家を解体!思い出を残そう

仮住まい先に引っ越したら、いよいよ家の解体です。
解体工事はかなり音が出るので、工事が始まる前に近隣にあいさつしましょう。
建築会社が同行してくれる場合もありますので、確認しましょう。
無事近隣挨拶が終わったら、いよいよ工事スタートです。
一般的サイズの木造住宅ですと、2週間から1か月程度で終了します。
今の姿を見る最後の機会なので、ぜひ写真や動画に残しておくようにしましょう。
後々完成した住宅と同じアングルで写真を撮れば、ビフォアアフターを
見比べることができます。
今までお世話になって家に感謝を込めて、解体される前に
その姿を写真や動画に収めましょう。
地鎮祭をしたら着工!
解体されると、建設地が更地になります。
工事着工の前に、工事の安全と土地へのご挨拶などのために
地鎮祭を行うことが一般的です。
地鎮祭を行う神社は、ハウスメーカーの場合は
ハウスメーカー側が手配してくれるのが一般的です。
ハウスメーカーが手配してくれる神社は、地鎮祭に慣れており、
必要なものをすべて用意してくれるので、施主としては楽ですね。
基本的に必要なものは初穂料(地鎮祭の代金)のみです。
初穂料は一般的に3万円~4万円程度です。
もしご自分で地鎮祭を行う神社を手配される場合は、注意が必要です。
地鎮祭に必要な竹や、海のもの山のものなど施主が用意しなければならない場合があります。
特に竹は、売っているところを探すのも、運ぶのも大変です。
雨の場合はテントを用意しなければなりませんが、基本的には
建築会社が用意してくれるはずです。
「雨降って地固まる」と言いますから、雨でも落胆することはありませんよ。
地鎮祭は、ハウスメーカー手配の神社を使うと、用意するものが少なくて楽。
地盤改良が家を支える

さあ、いよいよ建築工事が始まります。
着工金の支払いをしましょう。
まずは地盤改良工事から。
※地盤改良工事を行わない場合もあります。
地盤改良にはこの工法が一番良い!というものは基本的にありません。
建設地の地盤状態と、その上にのせる建物のバランスや重量で決まります。
地盤改良工事は、家が建ってしまうと見えなくなってしまう部分なので、
この機会に一度見ておくとよいでしょう。
地盤改良に正解なし!
見えなくなるので、この機会に見学しよう。
建物の大事な大事な基礎工事
建物の建築工事の中で、一番長く時間がかかるのが、この基礎工事でしょう。
それだけ大事な工程になります。
おおよそ一か月程度の期間となります。
基礎が出来上がった段階だと、不思議ですが家が小さいような気がします。
基礎完成段階の家を見て、小さく感じて不安になるかもしれませんが、
出来上がってくるとそうでもないので、ご安心ください。
建物の一番重要な基礎工事。
なぜか小さく感じますが、特に心配はいりません。
上棟して上棟式!
上棟金の支払いのタイミングです。
純粋な軸組み工法の木造住宅が減って、
2×4や鉄骨造の住宅が増えているため、
昔ながらの餅をまくような上棟式は少なくなっています。
ただ、別の方法で記念となるようなセレモニーを行う住宅会社もあります。
構造部分の壁に手形を残したり、家族の名前を書いた特別なボルトを占めたり。
一生の中で何度もできるわけではない家づくり。
家族で一生の思い出になるように、楽しみましょう。
様々な形の上棟式が存在します。
家づくりの思い出として大切にしましょう。
内装工事と外装工事

上棟すると、家の中外両方の工事が進んでいきます。
中は断熱材や窓が入り、フローリングなどの建材、設備が入ります。
外装工事は塗装やタイルなどの工事が並行して進められます。
いよいよ、家としての完成に近づいていきます。
内装工事中に、実際の部屋を見てコンセントを増やしたいなどの場合は、
担当営業に相談してみましょう。嫌がられるとは思いますが(笑)
対応してくれることもあります。
いよいよ家としての形が出来上がってきます。
実際の部屋を見て、コンセントの変更などがあれば相談しましょう。
家の印象を決める外構工事

家の打ち合わせになっていると、外構工事の打ち合わせがあっさりしてしまうことがあります。
しかし、外構工事こそ、家の印象を作り上げます。
外構の手を抜いていると、家自体にどんなにお金をかけていても、
見栄えの良い家にはなりにくいです。
ですが、家にそれほどお金をかけていなくても、
外構にしっかりとお金をかけると、非常に豪華な家に見えるのです。
様々な素敵な外構の家がありますので、参考にしながら素敵な外構を作り上げましょう。
外構業者は住宅会社が紹介してくれることがほとんどですが、
家の印象を決める外構工事。最後まで気を抜かないで!
もし知り合いがいれば、その業者を使うこともできます。
施主検査をして引渡し!

とうとう家の完成です。ここまで長かったですね。
引渡の一週間ほど前に、施主検査を行います。
実際に完成した家を確認し、引き渡しを受けて問題ないかどうかをチェックするのです。
チェックすると言っても、何をチェックすればいいんだと思う方へ、いくつか
チェック項目を挙げておきますので、ご確認ください。
- 床、壁に傷、汚れがないか
- 設備に傷、汚れがないか
- 窓、網戸は問題なく開閉できるか
- 内装のドアは問題なく開閉できるか
- コンセントなどは想定したところについているか
- ダイノックシート(木目のついたシール)がはがれているところはないか
- 外のタイルや塗装に、はがれているところはないか
- 外構の段差は均一の高さか
大体このようなところを見るとよいかと思います。
気になったところがあれば、伝えて問題ありません。
引渡までになおせるところはなおし、間に合わないところは
引渡後に対応してくれます。
さあ、施主検査をして問題なければ、無事引渡となります。
銀行ローンを実行し、引渡し金が振り込まれると
引渡しを受けることができます。
引渡では鍵の受け渡しや、各設備の説明、
取扱説明書の受け渡しなどが行われます。
やっと引渡ですね。お疲れさまでした。
引渡し後は、引越しや新しく買った家具家電を搬入することになると思いますが、
その前に掃除をしましょう。
もちろん引渡し前にクリーニングはしていますが、
それほどきっちりと行われているものではありません。
ですので、家具家電が何もない段階で、全体的に掃除をするとよいのです。
また、その際は家の各窓を開けて換気しましょう。家の中の壁紙などは
接着剤でついているため、新築時はその匂いが残っています。
敏感な方は気になって眠れないということもありますので、
しばらくは窓を開けてしっかり換気しましょう。
しっかりと施主検査をし、気になったことは伝えましょう。
引渡し後は換気しながら掃除をしましょう。
まとめ
ざっくりとですが、家づくりの流れについてご紹介してきました。
それぞれの項目について、もう少し深掘りした内容の記事も
今後書いていこうと思っていますので、お楽しみに!
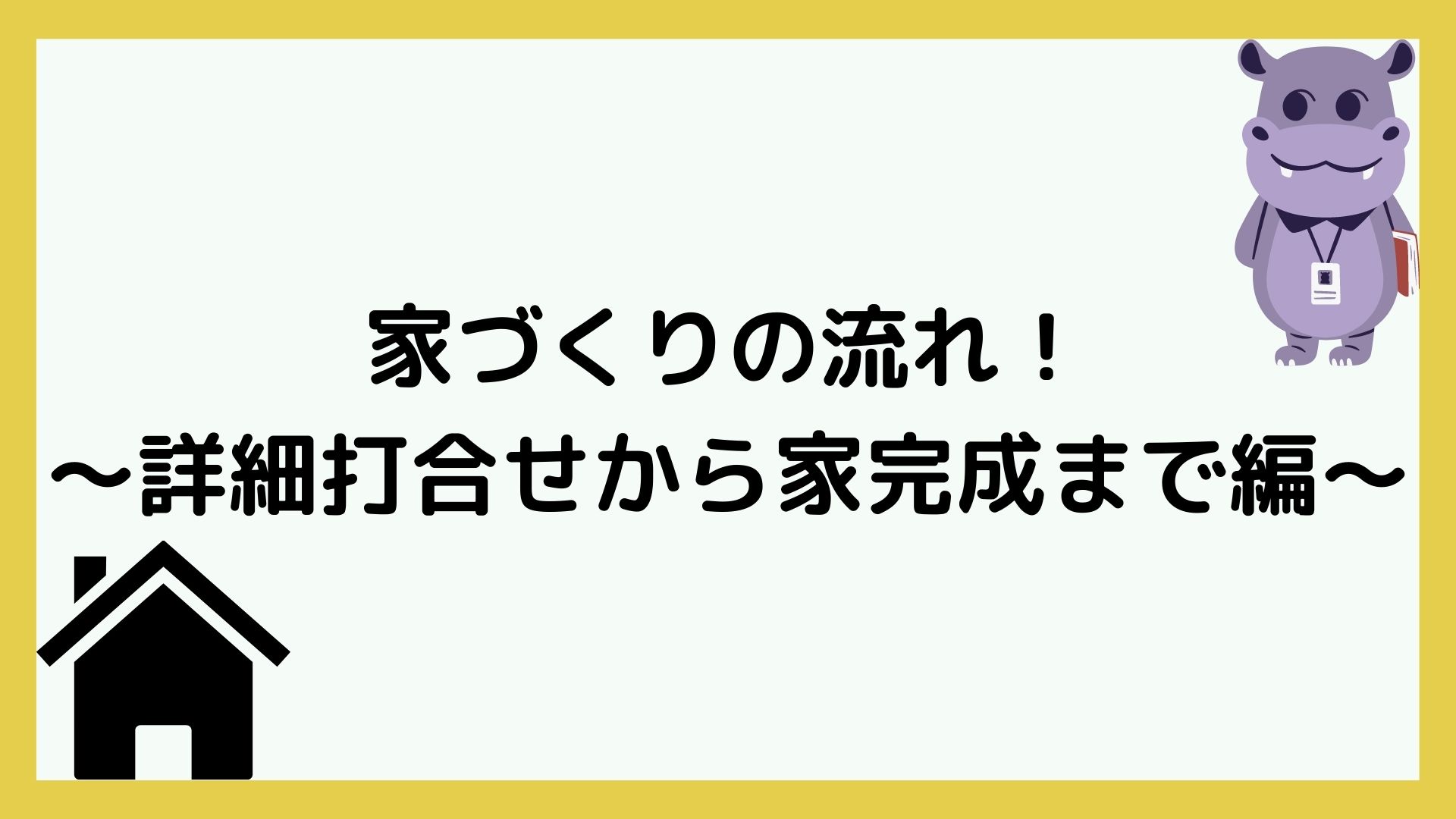
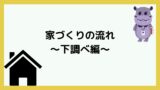
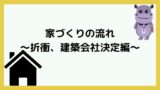
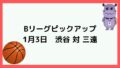
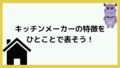
コメント